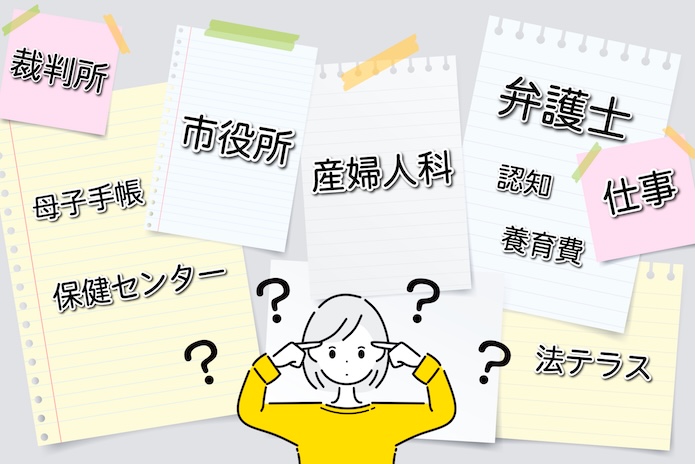未婚で産むことを決心してから、「じゃあ何をどうすればいいの?」の毎日。
今回は、そんな「未婚シングルで出産予定の方」と、一緒にひとつずつ整理していけたらなと思います。
とはいえ、私自身の体験をもとにまとめています。
必ずしも参考になるとは限りませんが、皆さんの「頭の整理」に少しでも役立てばうれしいです。
何の前触れもなく訪れた未婚シングルへの道

妊娠6か月手前、ある日突然彼から出産をやめてほしいと言われました。
理由はとんでもないものでしたが、その日まで普通に産めると思っていたので、とてもまともな精神ではいられませんでした。
色々な考えが巡って、どう過ごしていたのかも思い出せません。
ただ、もし今戻れるなら、あの時の私を抱きしめにいきたい。
自分でもそれくらいしかしてあげられないほどに辛い数日間でした。
たくさん葛藤しましたが、私は「産む」と決めました。
多くの否定的な意見も受けましたし、「子どもがかわいそう」と言う人もいました。
でも、私は産むと決めました。
いろんな未来を想像しても、やっぱりこの子と暮らす道を考えてしまう。
中期中絶は分娩と同じです。陣痛があり、出産して、死産届を出して、火葬・埋葬……。
それを想像したとき、私は心から「産みたい」と思いました。
この子に会いたい、笑顔が見たい。一緒に笑って生きてきたい。
それだけで十分な理由でした。
「子どもがかわいそうかどうか」は、子ども自身が決めること。
他人が判断することではありません。
私の人生に責任を持たない人たちに、世間の意見を代弁するような顔で意見されても気にしない。
「私が幸せにする」と決めたんです!
身重すぎて動けないけど、子どもが生まれたらもっと動けない!
出産を決めたとはいえ、先行きは不透明。 何からどう準備すればいいのか、全部が不安でした。
「妊婦だからこそ、妊娠中にできることを進めておきたい」 そう思い、私なりに調べて相談内容を大きく2つに分けて整理することにしました。
相談先を「制度」と「司法」に仕分ける
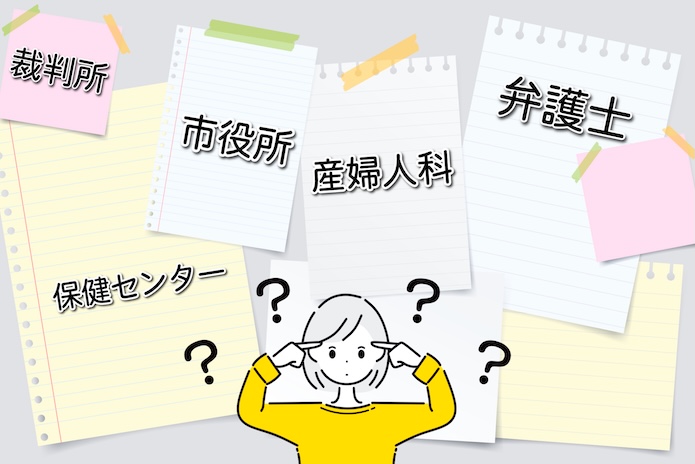
まずは焦らず、相談先を整理することが大事です。
弁護士さんにいきなり相談する前に、制度のほうで解決できることも多いです。
私が分けたのは「制度」と「司法」の2つ。
制度:役所・保健センター・産婦人科等
司法:弁護士・裁判所・司法書士等
振り返ればこの時に自分のナイス判断だったことは、慰謝料のことは一旦忘れて後で考えるようにしたこと。
後にこれがなぜナイスだったのか、別でまとめたいと思いますが、まずは子どもと自分が生きていくための手続きからです。
それでは、一緒に確認しながら分けていきましょう!
①産む病院は決まってますか?
とにかく一人で自宅で産もうと思わないでください。
ここで強く言いたいのは、産院は妊婦さんの見方です!
産みたいと言っているお母さん達をサポートしようとしてくれますので、色々不安だと思いますが、まずは産院を決めてください。
あなたが思っているよりも遥かに見方でいてくれますよ。
まだ受診できていない方や、病院の選び方が分からない時は、助産師外来をやっている産院をお勧めします。
生まれてくる赤ちゃんの関係で、必ず今の家族状況やお相手の事を聞かれますが、病院には包み隠さず話すことで、役所との連携も取ってくれます。
②母子手帳はもらってますか?
赤ちゃんの心拍が確認出来たら、いよいよ病院から「母子手帳をもらってきてね」と言われます。
- すでに貰ってる方は保健センター(もしくは交付された管轄課)に現状の電話をしてください。
- まだの方は、貰いに行く前に電話口で未婚シングルで産むことを話してください。
※電話での伝え方は、「未婚で産むことになったから今後の生活やひとり親として受けられる支援などはどういったものがあるのか、相談に乗ってほしい」みたいな感じで伝えてみてください。
あとは訪問だったり面談だったりの時に、役所への窓口や資料など準備してきてくれます。
私はわんわん泣きながら話を聞いてもらい、相談窓口などを教えてもらいました。
もしここで担当の人がいまいち親身ではなかった場合、担当変えてもらいましょう!
③お金の目処は立ちそうでしょうか?
相談する時に、「今の預金でどれくらいの間は生活していけそうか」を聞かれます。
ご自身の出産予定日と、その後数か月の生活が成り立つのかを計算してみてください。
- 収入がない人は保健センターに相談後、役所の窓口(福祉課など)へそのまま行ってみてください。
- 直接支払制度を利用しても費用が不安な人は、保健センターに窓口を教えてもらってください。
- 働いている人は産休、育休が取れるかを会社に確認してください(まだ未婚云々は伝えても伝えなくてもどちらでもいいです)
個人的にちょっと意外というか残念だったのが、保健センターと市役所は連携しているようで、お互いに制度など詳しく理解していないことが多かったです。
なので、最初からどちらの窓口にも行くと考えて予定に余裕を持たせていきましょう!
出産手当金、育休手当を申請予定の方、すぐには入りません!
出産手当金は出産日から3~4か月、会社の人事総務のスピード感によっては5~6か月後の場合もあります。
育休手当は、育休開始から2~3か月なので出産日から4~5か月後くらいです。
産休に入ってから5、6ヵ月は収入ゼロの頭でいてください!
④住む場所は確保できている?
同棲解消や実家に頼れない場合、住居の相談も必要です。
状況が整理できなくても、まずは現状を正直に話してみてください。
妊娠している人が入れるシェルターや、市役所で何かしらの案内をしてくれる場合があります。
⑤子どもの認知の話はどうなっていますか?
未婚で出産ということは、当然相手の戸籍にも子供の戸籍にもお互いの名前は載りません。
認知は子供の当然の権利です。そして、できれば妊娠中に片づけておけると産後だいぶ楽です。
認知には以下の3種類があります
・胎児認知(妊娠中でもOK)
・任意認知(出生後)
・強制認知(出生後→調停→裁判)
認知に関しては子供と彼のことになりますので、手続きは相手がすることになり、母親が勝手に届出をできるものではないのです。
細かいことは別の記事にしますが、今は認知してもらえるかどうかをまず把握して下さい。
弁護士や調停を考えるのは、それからです。
認知しないと決めているママさんは、窓口相談時に聞かれたら伝えてくださいね。
⑥養育費はどうする?
公正証書を作ることができればベストです。
ただし認知されていない場合、法的に養育費請求ができません。
なので、優先順位としては「出産>認知>養育費」です。
こちらも後で別記事にしますが、裁判所で調停となった場合でも、最初に認知調停からなので、今の優先度としてはちょっと低くなります。
気持ちとしては最優先にしたいところではありますが、「まずは出産するための優先度」として低くなるだけですので安心してくださいね。
養育費は子供の権利です。認知さえしていれば、払わなければなりません。
必ず貰うためにも、意思の確認を記録として文面でやり取りし、相手の意志がどうあれ貰える準備をしましょう!
仕分けたら相談先が見えてくる

とりあえず妊娠中に整理しておきたいことはこの6つ。以上を踏まえて、相談先を仕分けてみるとこうなります。
制度→①、②、③、④
司法→⑤、⑥(③、④)
制度の相談先
①~④は、窓口や管轄が違えど国や自治体の制度として何かしらの支援が受けられるのか、まずは保健センター(もしくは母子手帳を配布している窓口)から行きましょう。
「行政は大したことしてくれない…」
という人も多いですが、こちらから動かない限り、何もできないのが現状です。
特に出産に関しては、余程の自治体じゃない限りはSOSを出せばサポートしてくれます。
更に私たちのような人が助けを求めれば、特定妊婦として支援を受けられやすいです。
その為にも、まず①~④を把握して伝えることが最優先です!
もしあなたが今、何も準備できずとにかく涙があふれていっぱいいっぱいな場合は、一番最初に産院か保健センターどちらかに話してみてくださいね。
司法の相談先
⑤、⑥は弁護士相談が一般的です。
ここで注意していただきたいのが、認知や養育費の弁護士費用は他の案件より少し高いです!
最初から全部お願いするつもりで行くと、家計がかなり圧迫されてしまいます。
実際私も相談に行った際、
「着手金だけでも費用がけっこうかかる。出産や生活費に少しでも取っておいた方がいいから、自分で頑張れるとことまでやってみて拉致あかなければ依頼するでもいい」
とまで言われました(笑)
なるべく費用を抑えたい方は、認知の種類や調停を起こす際の流れなどを聞くための相談に行くといいでしょう。
(③、④)として入れた理由は、出産費用は相手にも請求できますので負担してもらいたい場合は一緒に相談するといいでしょう。
同棲してる方は弁護士に依頼した場合、当面の家賃や引っ越し費用を負担してもらえるか交渉してもらうのもアリです。
弁護士に相談するなら

慰謝料や養育費の話を進めたい場合でも、すぐに弁護士へ依頼するのではなく、まずは無料相談を活用しましょう。
- 離婚・家族問題に強い事務所の無料相談
- 市役所の無料法律相談
- 法テラス(3回まで無料)
費用を抑えたい場合は、まず制度や認知に関する情報収集のために相談し、本格的に進める段階で依頼するのがベターです。
でもやっぱり、体調が一番大事!

いくら自分で覚悟したからって、妊娠中の体やメンタルでやるのは本当に大変なことです。無理をすると出血や体調不良に繋がります。
体と心を大切にしながら、妊婦生活を少しでも前向きに過ごしてくださいね。
一つ頑張ったら、好きなもの食べたり休んだり自分を甘やかして妊婦生活も楽しんでください♡
長くなりましたが、少しでも誰かの役に立てていたら嬉しいです。
また次回、お会いしましょう!